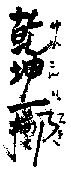
平成13年7月20日(152号)
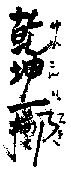
平成13年7月20日(152号)
| 何かちょっと異様である。参院選が始まって、全国遊説中の、小泉さんの動向をテレビカメラは執拗に追う。地方では、通過する列車を、各駅のプラットホームで、「小泉さんがんばって!」の横断幕を手にした女性群が出迎える。街頭に立つと小泉さん似顔絵入りのTシャツを着た若い女性たちが、人気タレントを追っかけるように、潤んだ目で見つめる。その数は尋常ではない。「じゅんじゅん」のメールマガジンが彼女たちの話題を集める。小泉さんへ支持率は、依然として、90
%を保っている。「改革」の掛け声だけでこんなに日本中が興奮しているのは、やっぱりおかしい、と野党でなくとも首を傾けざるを得ない。永田町の一部では、それに対して、ある珍説がまことしやかに囁かれている(週刊文春・6・28
号)、そうだ。それは「日本人 年集団ヒステリー周期説」である。 60年に一回、日本人はおかしくなっている、というものだ。60
年前には、太平洋戦争が勃発した。日中戦争が泥沼化し、国民には鬱々としたものがあった。それが「パールハーバー」で暗雲が吹き飛んだのである。その時、国民は、熱狂し、戦勝に狂っていた。惨めな敗戦を経験した現在では、想像はできないだろうが、それはそれは興奮の渦にいたのである。その60
年前は、明治維新直前、全国で、「ええじゃないか」という奇妙な踊りが大流行している。徳川幕府末期、世情不安、物価が高騰し、一揆・打ちこわしが起こった。そこで、民衆は「ええじゃないか。ええじゃないか」と歌いながら、男性は女装し、女性は男装して、仕事をほおりなげて、踊り狂って、全国あちこちで練り歩き、鬱憤を晴らしたのだ。同じようなものには、その60
年前に、500万人の日本人が、一斉に、伊勢神宮に参拝したという、「天保の御蔭参り」がある。この御蔭参りというものも、飢饉が起きたり、幕府の締め付けが厳しくなったり、社会不安に陥った時期に起きている。天保の59
年前には、「明和の御蔭参り」、その66 年前、富士山が爆発した頃の「宝永の御蔭参り」。なるほど、日本人は60
年に一回、集団で狂っているのである。今度の「小泉現象」もどうもこの類ではないか、と危惧する声には、うなずかざるをえない。確かに、政治不信や経済不安、社会のあらゆるところで閉塞状態が続いている。そんななか、森前総理の「誕生疑惑」から始まって、外務省機密費問題、KSD事件など、次々と腹の立つ事件が起きている。そこに「改革」という言葉を使って、テレビ映りが前の方よりましで、アジテーターとしての演説の巧みな小泉さんが登場。国民は、一気に不満を爆発させる。60
年ぶり、突如として、日本人は、「小泉・御蔭参り」を始めたのである。このことは、やっぱり異様としかいいようがない。政治というのはそういう訳にはいかないからである。ある特定の人物に絶対的権力が集まってしまうことは、恐ろしいことなのだから。 |
平成13年7月6日(151号)
| ブルーの「ラルフローレン」のシャツが急に売れだしたそうだ。アメリカで日本の総理大臣が、報道陣の前にそのシャツを着てあらわれた。通信衛生を通じて、テレビで放映される。それが、「かっこいい!」という訳である。小泉旋風はアメリカからも吹き荒れている。キャンプデービットの大統領山荘での、ブッシュさんとの会談の内容よりも、小泉さんが着ていたものに注目が集まっているのだ。テレビの威力は政治を根底から変えつつある。■宍戸錠さんが、本を出した。ほっぺたを手術で膨らましていたが、それを除去することにして、その経緯を綴りながら、映画界へデビューしたころのエピソードを披瀝している。「シシドー、小説日活撮影所」という本である。それによると、頬を膨らませたのは、1956年、昭和
年である。そのころは、まだ、テレビは、家庭で観る時代ではない。華やかな映画スターたちの動向は、映画雑誌が取り上げ、若者たちは、封切られる映画を観るために、どっと映画館に押し寄せた。宍戸錠さんは、日活の第一期ニューフエイスとして、映画界に入った。その後、ライバルが続々と現れる。石原裕次郎、小林旭、赤木圭一郎。彼らと伍して映画スターをやって行くためには、それ以上に目だたなければならない。だれも考えつかなかった、豊頬手術に踏み切る。ちょと顔の様子が変わって、抜擢されたのが、小林旭「渡り鳥シリーズ」の、敵役、「エースのジョー」。無国籍映画と酷評されたが、このシリーズは大ヒットする。どこの映画館も鈴なりの盛況。田舎の映画館の周辺には、農耕馬にまたがり、白いマフラーをなびかせて、ギターを肩に引っかけた青年が現れたりした。映画は、日常での大きな話題だったのだ。そのころ、政治のことを映像で知る機会は唯一映画館で、だった。2本立ての映画の休憩をはさんだ間に、次週予告編のあと、ニュースが始まる。それも
分間ぐらいの時間、その頃の大きな話題がまとめられ、おおざっぱに世間のことを知ることができた。政治のことは、ほとんど国会周辺で起きるデモのシーンだった。それが、
年近くたって、茶の間にテレビが出そろってしまうと、主役交代である。華やかだった映画スターは、そのシンボルだった頬を削り取ることでやっとスポットを浴び、暗い映画館の中では一瞬しか登場しなかった総理大臣が、アメリカに政府専用機で飛んでいき、ブルーの「ラルフローレン」で颯爽とテレビに現れ、支持率に大きな影響を与える。何か、恐ろしい時代になったもの、である。 |
平成13年6月15日(150号)
| 「米百俵」という言葉が日本中を駆け回っている。明治維新後の、越後・長岡藩、「藩建て直し」の逸話である。5月7日、小泉首相の所信表明演説に、突然、飛びだした。「今こそ、米百俵の精神」が必要だと、高視聴率の国会中継で、小泉さんが訴えたのである。一瞬、どこのどういう時代の話なのだ、と正直戸惑った。あまり聞いたことがなかったからだ。それが、一月もしないうちに、日本中を蹂躪してしまった。いわゆるブームになったのである。長岡市では、「米百俵まんじゅう」と、清酒「米百俵」が爆発的に売れだし、ツアー客が全国から押し寄せてくるようになった。市の観光に一役かってくれた小泉首相を、市長が訪問してお礼を申し上げるという、思いもかけない事態に、長岡市はうれしい悲鳴をあげている。藩の財政建て直し、のエピソードはあちこちにゴマンとある。長岡藩には、司馬遼太郎の「峠」で有名な河井継之助がいる。その「米百俵」の主人公・小林虎三郎が、同じ長岡藩の、同時代の人物だったとは、意外だった。小林虎三郎は、幕末の佐久間象山の「象山塾」で、吉田松蔭(寅次郎)と机を並べている。象山塾の「二虎」と並び称されていたが、松蔭は小林虎三郎の智力には一目も二目も置いている。虎三郎は、幕府がアメリカとの通商の窓口とした函館と伊豆の下田に、長岡藩主を通じて、異議を唱える建白書を具申した。下田でなく横浜にすべき、という考えである。それが、藩主の怒りにふれ、江戸から、長岡に呼び戻され、幽閉の身となる。小林虎三郎、
歳の時である。幕末の動乱を駆け回る若者たちのなかに、小林虎三郎の名前がどこにもみあたらないのは、そういう事情があったからだ。幼少の時の「疱瘡」で、顔中あばた。左目は失明してしまった。同世代の少年たちには、からかわれ、いじめにあう。父親には、そんなものを相手にしても、左目が見えるようになるわけでもない、それよりも、「己に勝て」と教えられる。
代の働き盛り、 年の幽閉中にも勉学の意欲は衰えなかった。そして、いよいよ出番がやってくる。戊辰戦争で新政府軍からの攻撃を受けて、長岡藩は、壊滅状態となる。藩民たちに食べさせる米も払底。そこにお隣の藩から、「百俵のお米」が届けられる。これで飢えが凌げる、と藩士たちは大喜びするが、小林虎三郎だけが、反対する。藩民に配っても、五合ぐらいの割当てにしかならない。それよりも、今、我慢をして、国家百年の計をたてる。これを資金にして、人材を育てる「学校」を作るのだ、藩を立て直すには、先の見える人材養成が急務だ、と主張した。「国漢学校」が建設され、身分にとらわれず、「学びたいものには誰にでも」、勉学の機会を与えて、「ひと」を育てていったのだ。この話が、130年たった今、にわかに脚光をあびているのである。 |